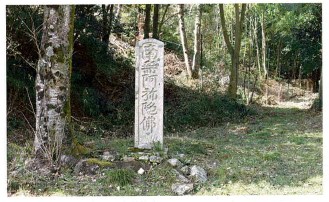結婚式
昭和五十年頃までは、見合い結婚が主流であった。お互いの親同士が結婚相手を決めたり、親戚や知人が縁談の話をもってきた。今のように本人同士の恋愛感情から結婚するのは稀であった。特に、昭和初期までは親が決めた結婚であり、結婚式当日に初めて相手の顔を見るという、今では想像もつかない結婚話も聞く。人と人との結婚ではなく、家と家との結婚であった。
昭和五十年代頃までの一般的な結婚式の流れ
男性側

「きめさけ」結婚話が整うと、仲人が女性宅に祝い酒を持参する。
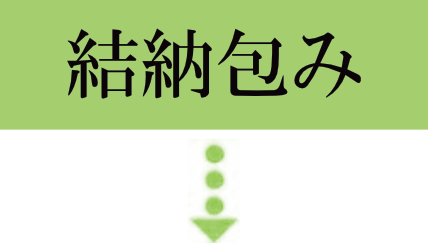
親戚を自宅に招き、結婚が決まった事を報告する祝宴。仲人が女性宅に結納金を持参する。
女子側
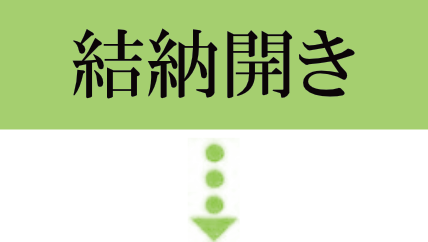
親戚を自宅に招き、結納を受け取った事を報告する祝宴。
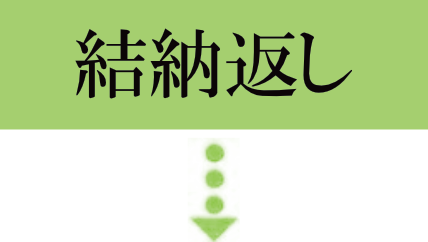

結納返しの飾り
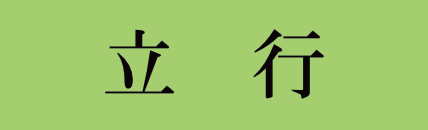
結婚式当日または、前日に親戚を招き門出の祝宴。
結婚式当日
花嫁宅では、朝から親戚一同が集まり、トラックに荷物を積み込む。トラックを先導し、花婿宅に花嫁道具を届ける役を荷宰領(にざいりよう)という。一般的に花嫁の親戚代表が務める。一方、花婿宅では届いた荷物を搬入するため、親戚一同が待機している。
タンスなど重い荷物の搬入は、青竹を杖にして前後二人が棒で担ぐ。青竹は用が済めば二度と使うことがないように玄関口で割ってしまう。縁起担ぎである。
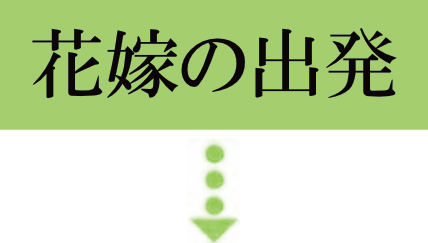

仲人が花嫁を迎えに行く。花嫁は親戚や集落の多くの見物人に見送られタクシーに乗り実家を出発。
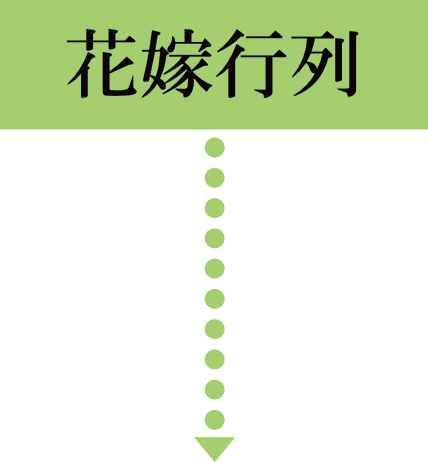


花婿宅の百メートル程手前でタクシーを降り、仲人夫妻を先頭に「長持唄」を歌いながらゆっくりと歩く。花嫁の両側には給仕役の二人の女児が付きそう

花嫁の土産として、見物人にお菓子を配る。
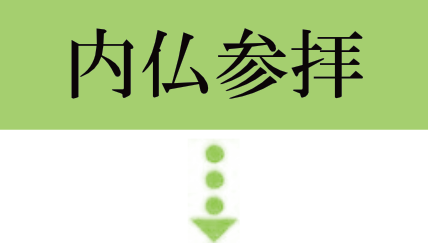
花婿宅に入るとまず、仏壇にお参りをする。
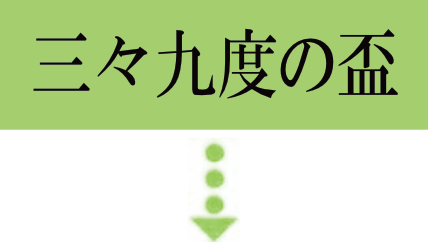
座敷では祝宴の準備が始まる。
別室(寝間)では、三々九度の盃が行われる。花婿・区長・両親・兄弟等。二人の女児が給仕をする。

花嫁と仲人が宴会場に入り、花嫁の紹介をする。祝宴は三時間以上続くこともあり、お色直しをした花嫁は、花婿と共に招待客に酒を注いでまわる。
結婚式翌日
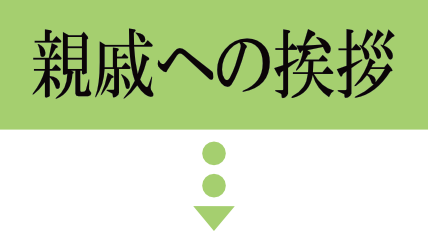
花嫁は義母に案内されて集落内の親戚へ挨拶に回る。

両家の主な親戚が集まり自己紹介。末永いお付き合いを誓う。
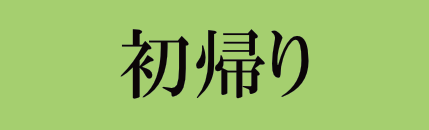
「三日帰り」とも言う。結婚式が終わり、二〜三日後に花嫁は実家に帰り、無事に嫁いだことを報告する。現在は、式後すぐに新婚旅行に出発する。
昭和の終わりから平成にかけ、結婚式はホテルなど結婚式場で行うようになり、また結婚には必ず必要であった仲人の制度もなくなった。「長持唄」を唄いながらの花嫁行列の光景はもう見られなくなってしまった。
結婚後の習慣
お寺参り
嫁ぎ先の菩提寺へ挨拶に行く。
かまど見せ
結婚式が終わり、落ち着いた頃に主な親戚が花嫁を招待する。「かまど」台所を花嫁に見てもらい、行事の時には手伝いをお願いするという意味。行事とは、冠婚葬祭や法要のこと。
五月見舞い
嫁の実家から田植え時の農繁期に労をねぎらうために、「焼き鰭」を持って行く習わし。
*婿側からは、年末に「獅・ブリ」を持って行くことがあった。ブリは出世魚であり男ブリを示す意味。
中元・歳暮
嫁の実家は、中元と歳暮の付け届けをした。また、男児が生まれると「鯉のぼり」女児が生まれると「ひな壇」を贈った。その後は、孫に中元と歳暮に履き物や衣類などを届けた。孫が大勢いれば実家は出費がかさなった。
現在のように男女平等という社会ではなかった。「娘を嫁にもらっていただいた」という男尊女卑の考え方であった。そのため、嫁の実家は嫁ぎ先に礼儀を欠くことはできず五月見舞い、中元、歳暮等の付け届けは、その例である。
農家に嫁ぐのはイヤ
農家に嫁いだ女性は経験の有無を問わず、農作業をするのは当然であった。出産、育児、食事の準備、夫の両親と同居。面倒な親戚付き合い。高度経済成長時代に突入すると、農家へ嫁ぐことを避ける女性が増え、農家の嫁不足が全国で深刻な問題になってきた。夫は会社で働くため「三チャン農業」と言う言葉が流行した。農業に従事するのは「じいチャン、ばあチャン、かあチャン」である。今では、「かあチャン」もしなくなり、女性が外で働く時代になった。
葬 式
家族の誰かが亡くなるとすぐに、主な親戚が集まり葬式の日程や僧侶への連絡など役割分担の相談が行われる。日程が決まると集落内の親戚が集まり葬式の準備に取りかかる。
男性の仕事
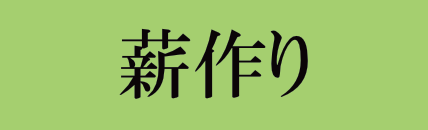
火葬に使用する広葉樹の木を山で切り倒し薪を作る。

花瓶に立てる華(四華)を作る。男は金色の紙、女は銀色の紙で作る。
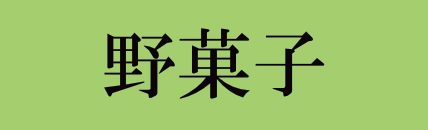
墓場に飾る野菓子。立方体の枠に菓子を張り付けた飾り。
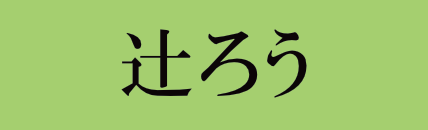
家から墓場までの道に立てる蝋燭。1メートル程の竹に蝋燭を付ける。
女性の仕事
自宅で葬式をするため、家の片付けと掃除。そして、手伝いに来る人のための食事の準備。また、「通夜」には親戚全員が参列するため、参列者全員の食事の準備は大変であった。葬式当日は主な親戚の家族全員の朝食も準備していた。現在は葬儀場や料理店に注文するので、女性は食事作りからは解放された。
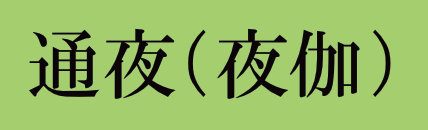
葬儀の前日夜七時頃から通夜が勤められた。参列者全員に食事を準備していた。
葬式当日
葬式を「告別式」とも言うが、真宗では「葬儀式」と呼ぶ。別れを告げるのではなく、仏との出逢いである。

朝の六時頃から、集落の親戚以外の人からの悔やみを受ける。

斎宿(ときやど)
集落内の親戚の食事場所として親戚宅を借りる。
他所宿(たしょやど)
他所からの弔問客の食事場所として親戚宅を借りる。

自宅の仏間で読経。喪主に次いで家族や親戚が焼香。葬儀には、親戚だけでなく集落内のほとんどの人が参列している。
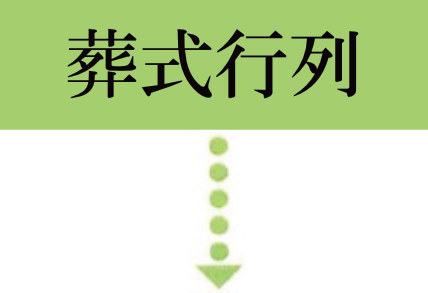
読経が終わると、いよいよ出棺。喪主は白装束にわら草鞋。家族の女性は喪服で履物は履かず白足袋のままで墓場まで行列をつくった。

昔は墓地のことを「三昧」(さんまい)と呼んでいた。墓地で遺族、親族、一般参列者も参列して葬儀が行われていた。
納棺について
今では、すべて葬儀業者にお任せであるが、かつては身内のものが遺体を一メートル四方の座棺に納棺していた。小さい棺であるため足や腕を折り曲げて納棺していた。その際、ボキボキと骨が折れる音がした。
火葬について
縦・横約百五十cm、深さ約九十cmの中へ棺を納める。棺の周囲に薪を縦にぎっしりとつめ込む。その上にムシロ二枚をかぶせ、角の四カ所から火をけ、蒸し焼き状態を保つように火葬する。深夜に二度ほど焼け具合を確認に行く。
菅江の火葬場